「生成AIを導入したものの、社内で活用が進まない」「一部の社員しか使っていない」といった悩みを抱える企業が多いのではないでしょうか。実際、多くの企業が生成AIツールを導入しても、全社的な活用には至らず、期待していた効果を得られずにいるのが現状です。
しかし、株式会社SHIFTは異なります。同社は半年で活用率を3倍に向上させ、実績800件、年間1500万円のコスト削減を見込むという驚異的な成果を上げています。そして、この成功体験を「生成AI 360度」というサービスとして体系化し、他社への支援も開始しました。
この記事では、SHIFT社が実践してきた生成AI活用定着の5つのプロセスを詳しく解説し、あなたの会社でも同様の成果を上げるための具体的な方法をお伝えします。読み終える頃には、生成AI導入の全体像が明確になり、明日から実践できる具体的なアクションプランが見えてくるはずです。
目次
- 1 SHIFT社の「生成AI 360度」とは?全社的活用を実現する包括的アプローチ
- 2 プロセス1:使いやすい環境提供 – 誰でも簡単に使えるノープロンプト生成AIツール
- 3 プロセス2:ユーザー分類とKPI策定 – データに基づく戦略的アプローチ
- 4 プロセス3:段階的な教育と興味喚起 – 全社員を巻き込む仕組み作り
- 5 プロセス4:部門別カスタマイズと成果創出 – 実務に直結する価値提供
- 6 プロセス5:全社共有とコミュニティ形成 – 持続的な活用文化の構築
- 7 SHIFT社のAIソリューション全体像 – ビジネス変革とIT変革の両輪
- 8 まとめ:生成AI活用定着への具体的アクションプラン
- 9 よくある質問(FAQ)
SHIFT社の「生成AI 360度」とは?全社的活用を実現する包括的アプローチ
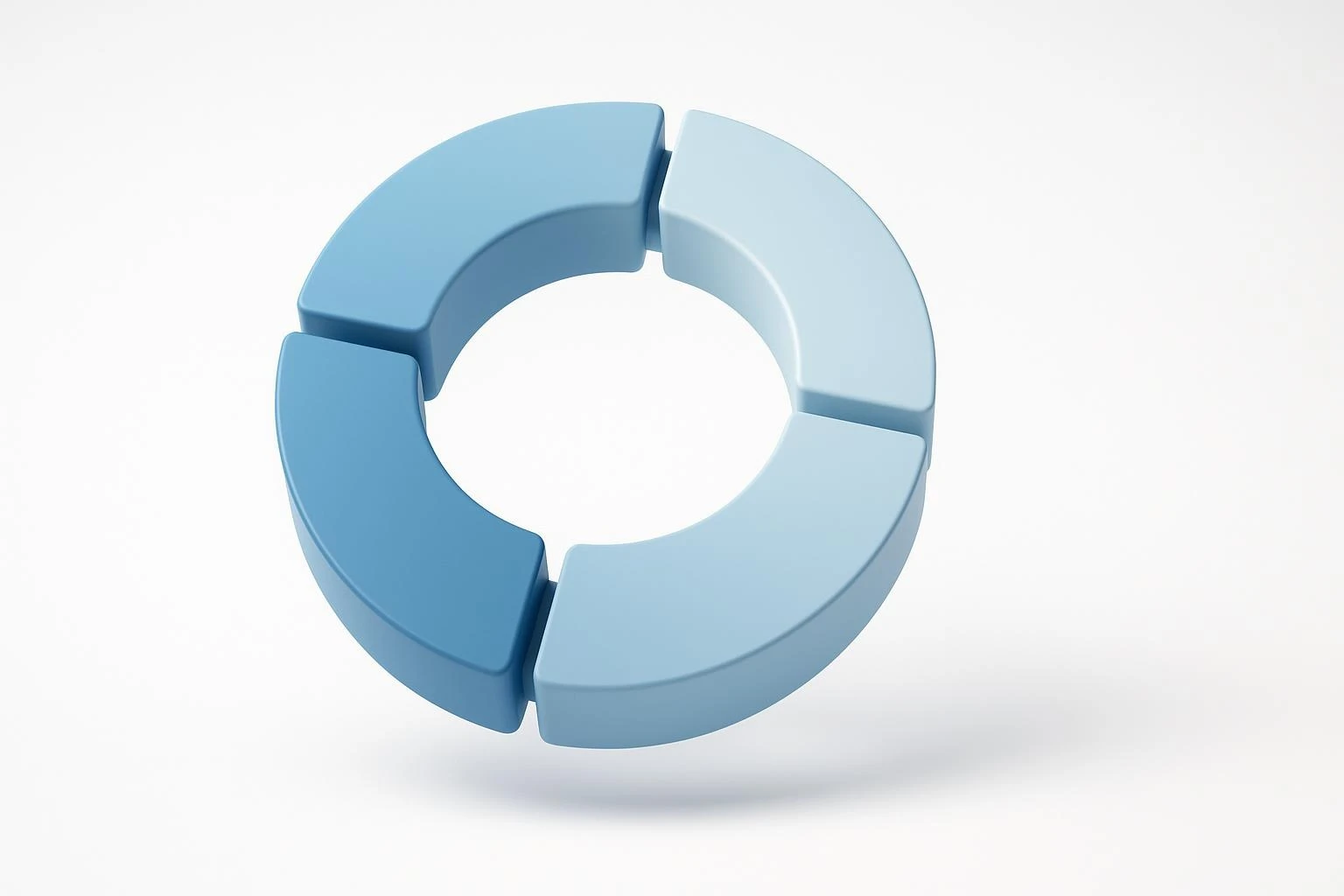

SHIFT社の「生成AI 360度」は、同社が自社で実践してきた特に効果の高かった取り組みを体系化したサービスです。単なるツール導入ではなく、全社的な活用方針策定からツール導入、カルチャー醸成までを一貫してサポートする包括的なアプローチが特徴です。
このサービスの核心は、生成AIの活用を「点」ではなく「面」で捉えていることです。つまり、特定の部署や個人の活用にとどまらず、組織全体で生成AIが自然に使われる環境を構築することを目指しています。
具体的には、以下のような要素を組み合わせた総合的な支援を提供します:
- 機会創出:業務に最適化された生成AIツールの開発・導入
- 生成AI利用環境提供:安全で使いやすい利用基盤の構築
- ユーザー分類・KPI策定:利用状況の可視化と目標設定
- 研修・勉強会:スキルレベルに応じた教育プログラム
- 興味関心コンテンツ:無関心層への働きかけ
- 業務棚卸し・プロンプト作成:実務に直結する活用方法の開発
- コミュニティ・コンテスト:社内文化としての定着促進
これらの取り組みにより、SHIFT社は自社内で生成AI活用率を大幅に向上させ、その知見を基に他社への支援サービスを展開しているのです。
プロセス1:使いやすい環境提供 – 誰でも簡単に使えるノープロンプト生成AIツール

生成AI活用定着の第一歩は、誰でも簡単に使える環境を整備することです。SHIFT社では「天才くん」と呼ばれるノープロンプト生成AIツールを導入し、技術的なハードルを大幅に下げています。
従来の生成AIツールでは、効果的な結果を得るために複雑なプロンプト(指示文)を作成する必要がありました。しかし、これは多くの社員にとって高いハードルとなり、活用が進まない大きな要因でした。
ノープロンプトツールの導入により、以下のような効果が期待できます:
- 学習コストの削減:複雑なプロンプト作成技術を習得する必要がない
- 即座の活用開始:導入初日から実務で使用可能
- 品質の安定化:個人のスキルに依存しない一定品質の出力
- 心理的ハードルの低減:「難しそう」という先入観の解消
実際に、楽天モバイル株式会社では自社開発の生成AIを全社員に展開し、利用率85%を達成。週平均4.9時間の業務効率化を実現しています。このように、使いやすい環境の提供は、全社的な活用促進の基盤となる重要な要素なのです。
また、SHIFT社では使いやすく安全な生成AI利用環境の提供も重視しています。セキュリティ面での不安を解消し、社員が安心して業務で活用できる基盤を整備することで、より積極的な利用を促進しています。
プロセス2:ユーザー分類とKPI策定 – データに基づく戦略的アプローチ
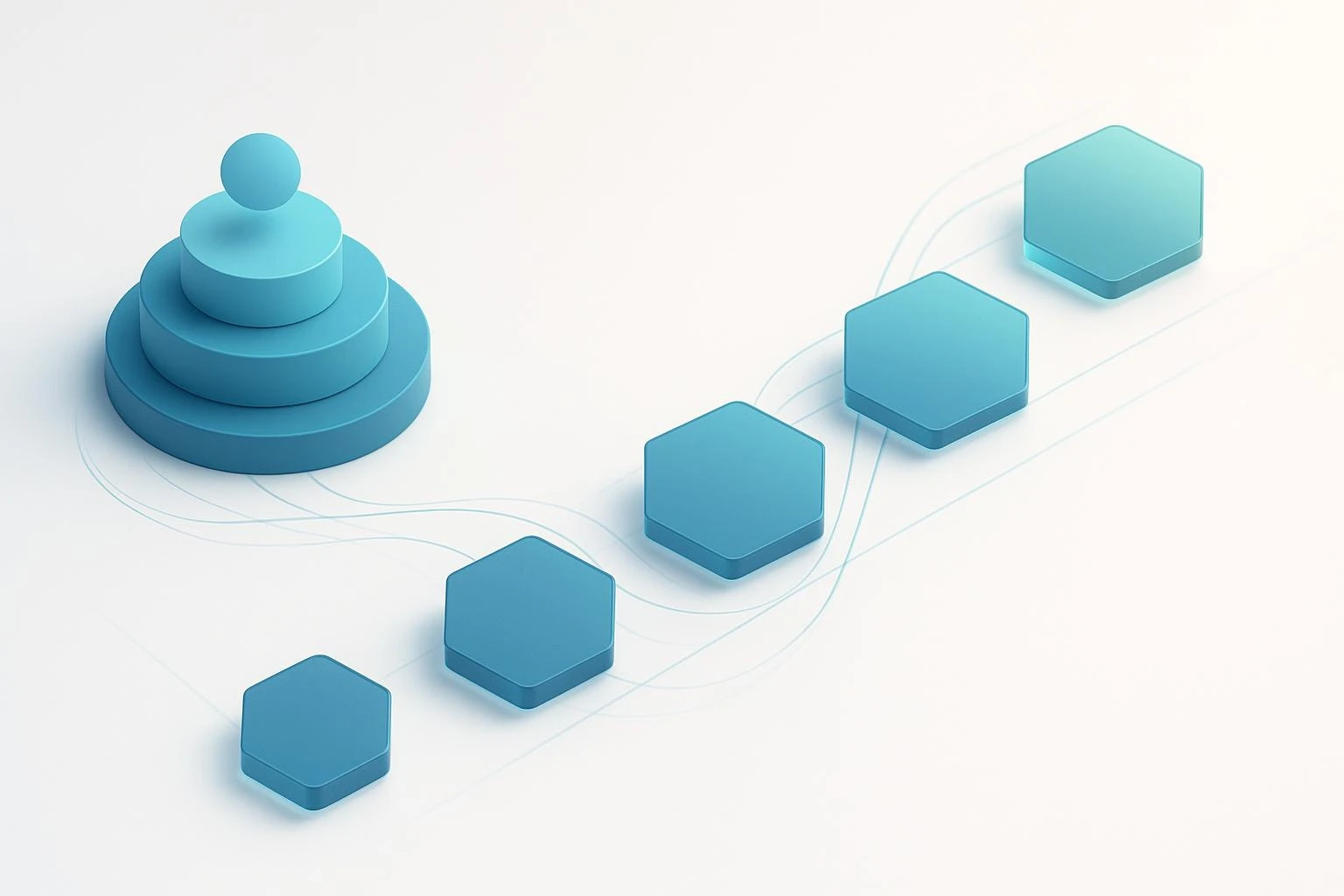
環境整備の次に重要なのが、生成AIの利用ログを分析し、AI適用業務やユーザー層を可視化することです。SHIFT社では、この分析結果に基づいてKPIや社内ユーザー向けのガイドラインを整備し、トップダウンでの生成AI利用推進を強化しています。
具体的なユーザー分類の例として、以下のような層に分けて戦略を立てることが効果的です:
| ユーザー層 | 特徴 | アプローチ方法 |
| アーリーアダプター | 積極的に新技術を試す | 高度な機能提供、事例共有の推進役 |
| 業務活用層 | 効果を実感し定期利用 | より高度な活用方法の教育 |
| 様子見層 | 興味はあるが未活用 | 成功事例の紹介、簡単な体験機会提供 |
| 無関心層 | 生成AIに関心が薄い | 部署別人気ツールランキングなど間接的アプローチ |
KPI策定においては、単純な利用率だけでなく、以下のような多角的な指標を設定することが重要です:
- 利用率:全社員に対する月次アクティブユーザーの割合
- 業務効率化時間:生成AI活用による作業時間短縮効果
- 品質向上指標:アウトプットの品質改善度合い
- コスト削減効果:外注費削減や人件費効率化の金額
- 新規活用事例数:月次で生まれる新しい活用パターン
株式会社ホットリンクでは、社員の生成AI利用率を10ヶ月で19.5%から59.8%に引き上げることに成功しています。これは、体制整備と社員巻き込み施策(AI活用推進チームの設置、教育プログラムの実施)を組み合わせた結果です。
データに基づく戦略的アプローチにより、各ユーザー層に最適化された施策を展開し、全社的な活用促進を効率的に進めることができるのです。
プロセス3:段階的な教育と興味喚起 – 全社員を巻き込む仕組み作り

ユーザー分類に基づいて、SHIFT社では未利用者やプロンプト初心者向けのハンズオン型勉強会を実施し、さらに無関心層向けに部署別人気ツールランキングを定期発信することで、社内ユーザーの行動変容を促進しています。
この段階的アプローチの特徴は、対象者のレベルや関心度に応じて異なる手法を使い分けていることです。
未利用者・初心者向けの取り組み
- ハンズオン型勉強会:実際に手を動かしながら学べる実践的な研修
- 基礎的なプロンプト作成講座:効果的な指示の出し方を段階的に習得
- 業務別活用事例紹介:自分の業務に直結する具体例の提示
- 1対1サポート:個別の疑問や課題に対応するメンタリング
無関心層向けの取り組み
- 部署別人気ツールランキング:競争心理を活用した関心喚起
- 成功事例の定期発信:同僚の成果を通じた間接的な動機付け
- 業務改善コンテスト:ゲーミフィケーションによる参加促進
- 経営層からのメッセージ:トップダウンでの重要性の伝達
重要なのは、押し付けではなく、自然な関心を喚起する仕組みを作ることです。部署別ランキングのような間接的なアプローチは、「自分も使ってみようかな」という自発的な動機を生み出し、持続的な活用につながりやすいのです。
プロセス4:部門別カスタマイズと成果創出 – 実務に直結する価値提供

教育と興味喚起の次の段階では、人事の応募書類分析や営業の提案書品質向上など、部門ごとの課題に合わせた生成AIツール作成を行います。これにより、各部門が実際の業務で具体的な成果を実感できるようになります。
部門別カスタマイズの具体例を見てみましょう:
| 部門 | 課題 | 生成AI活用例 | 期待効果 |
| 人事部 | 応募書類の大量処理 | 履歴書・職務経歴書の自動分析・評価 | 選考時間50%短縮 |
| 営業部 | 提案書の品質向上 | 顧客情報に基づく提案書自動生成 | 受注率20%向上 |
| マーケティング部 | コンテンツ制作の効率化 | SEO記事・SNS投稿の自動生成 | 制作時間70%削減 |
| カスタマーサポート | 問い合わせ対応の標準化 | FAQ自動生成・回答テンプレート作成 | 対応時間30%短縮 |
| 総務部 | 議事録作成の負担 | 会議音声からの議事録自動生成 | 作成時間80%削減 |
部門別カスタマイズで重要なのは、以下の点です:
- 現場の声を反映:実際の業務担当者からヒアリングを行い、真の課題を把握
- 段階的な導入:小さな成功から始めて、徐々に適用範囲を拡大
- 効果測定の仕組み:導入前後の比較ができる指標を設定
- 継続的な改善:利用状況に応じてツールを調整・最適化
このように、各部門の具体的な課題解決に生成AIを活用することで、「使ってみたら本当に効果があった」という実感を社員に提供し、自発的な活用拡大を促進できるのです。
プロセス5:全社共有とコミュニティ形成 – 持続的な活用文化の構築

最終段階では、部門間で得られた成果や知見を全社で共有し、共通ナレッジとして活用していきます。さらに、社内コミュニティやコンテストを通じて、生成AI活用を社内文化に根づかせることが重要です。
全社共有の仕組みとして、以下のような取り組みが効果的です。
成果共有の仕組み
- 月次成果発表会:各部門の活用事例と効果を定期的に共有
- ベストプラクティス集:成功事例をドキュメント化し、社内で検索可能に
- 失敗事例の共有:うまくいかなかった事例も含めて学習機会を提供
- ROI計算結果の公開:具体的な数値効果を透明化
コミュニティ形成の取り組み
- 生成AI活用コンテスト:創意工夫を競い合う場の提供
- 社内勉強会の自主開催:社員主導の学習コミュニティ形成
- メンター制度:上級者が初心者をサポートする仕組み
- アイデア投稿プラットフォーム:新しい活用方法を気軽に提案できる場
持続的な活用文化を構築するためのポイントは以下の通りです:
- 自発性の重視:強制ではなく、自然な参加を促す仕組み作り
- 継続的な刺激:定期的なイベントや新しい取り組みで関心を維持
- 成功の可視化:個人・部門・全社レベルでの成果を明確に示す
- 学習機会の提供:常に新しい知識やスキルを習得できる環境
このように、組織全体で生成AI活用を文化として定着させることで、一時的なブームではなく、持続的な競争優位性を構築することができるのです。
SHIFT社のAIソリューション全体像 – ビジネス変革とIT変革の両輪


SHIFT社の生成AI支援サービスは、単なるツール導入支援にとどまらず、ビジネス変革とIT変革の両輪でクライアント企業の競争力向上を支援しています。
同社のAIソリューションは大きく以下の4つの領域に分かれています:
1. コンサルティング・ガイドライン策定
- AI導入戦略の立案:企業の現状分析から最適な導入計画を策定
- ガイドライン作成:安全で効果的なAI活用のためのルール整備
- 導入支援:実際の導入プロセスにおける伴走支援
2. AIツール・パッケージ提供
- 業界特化型ツール:各業界の特性に合わせたAIソリューション
- 汎用的なパッケージ:多くの企業で活用できる標準的なツール群
- カスタマイズ対応:企業固有の要件に応じた個別開発
3. プラットフォーム提供
- 統合プラットフォーム:複数のAIツールを一元管理できる基盤
- セキュリティ機能:企業レベルのセキュリティ要件に対応
- 運用管理機能:利用状況の監視や効果測定が可能
4. 自社サービスでの実証
- テスト支援サービス:SHIFT社の主力事業でもAIを積極活用
- 実績に基づく改善:自社での実践結果を基にサービスを継続改善
- リアルな事例提供:机上の空論ではない実践的な知見の共有
特に注目すべきは、「AIによるIT変革」がSHIFT社らしい特徴だという点です。同社はもともとソフトウェアテストやQA(品質保証)を主力事業としており、その領域でのAI活用知見が豊富です。この専門性を活かして、他社では提供できない独自の価値を創出しています。
また、「自分たちのテスト支援サービス内容の中でも使っています」という点も重要です。自社で実際に使って効果を確認したツールやノウハウを提供するため、クライアント企業にとって信頼性の高いソリューションとなっているのです。
まとめ:生成AI活用定着への具体的アクションプラン
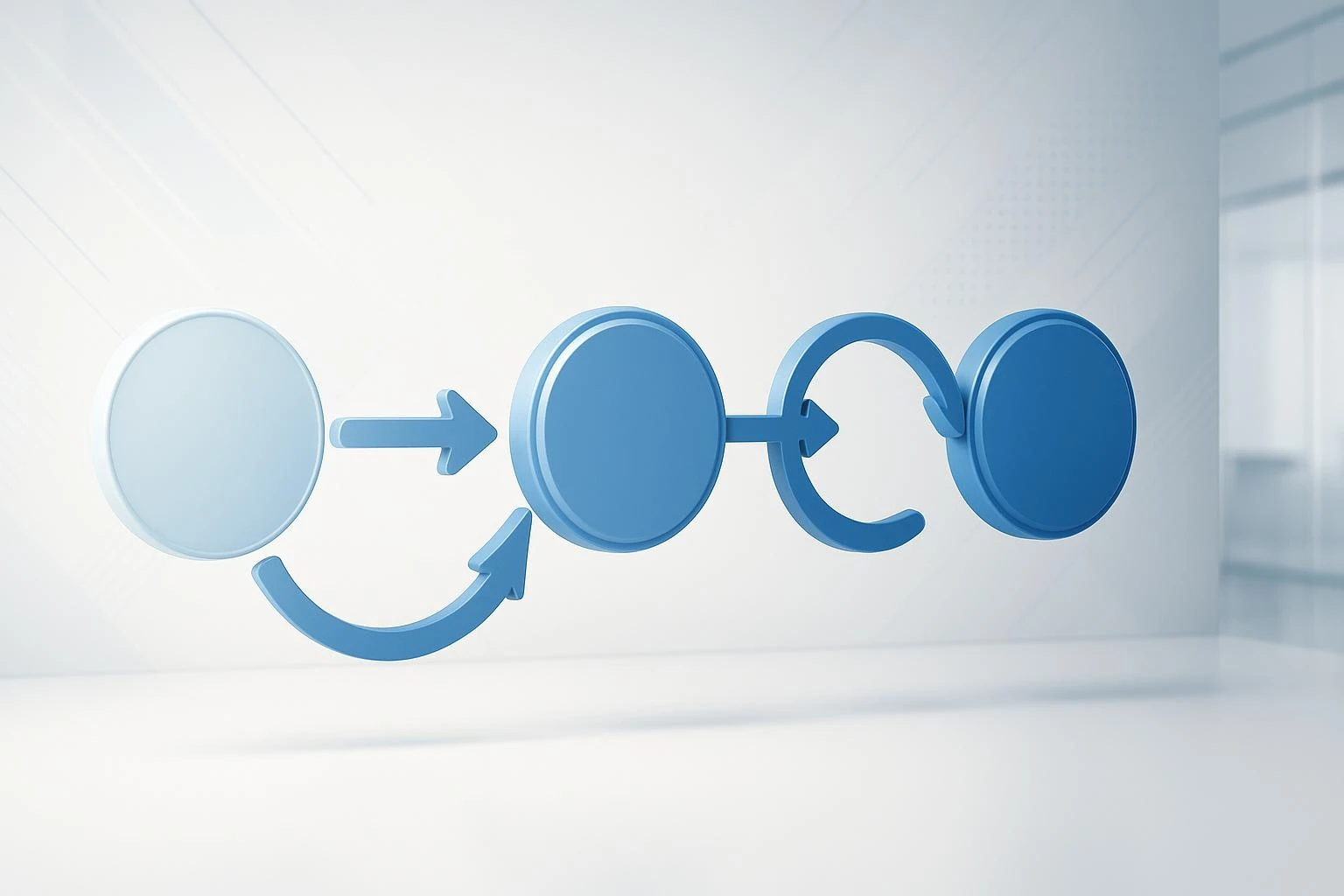
SHIFT社の事例から学んだ生成AI活用定着の5つのプロセスを、あなたの会社でも実践するための具体的なアクションプランをまとめます:
今すぐ始められる第一歩
- 現状把握:社内の生成AI利用状況を調査し、ユーザー層を分類する
- 環境整備:ノープロンプトツールの導入を検討し、安全な利用環境を構築する
- パイロット部門の選定:最も効果が期待できる部門で小規模な実証実験を開始する
中期的な取り組み(3-6ヶ月)
- KPI設定と測定:利用率、効率化時間、コスト削減効果などの指標を設定し、定期的に測定する
- 教育プログラムの実施:レベル別の研修や勉強会を継続的に開催する
- 成功事例の創出と共有:具体的な成果を上げた事例を社内で積極的に共有する
長期的な文化構築(6ヶ月以上)
- コミュニティ形成:社内勉強会やコンテストを通じて自発的な学習文化を醸成する
- 継続的な改善:利用状況や効果を基に、ツールや運用方法を継続的に最適化する
- 全社展開:成功した取り組みを他部門にも水平展開し、組織全体の競争力を向上させる
重要なのは、一度に全てを実現しようとせず、段階的に取り組むことです。SHIFT社も半年かけて活用率を3倍に向上させており、持続的な取り組みが成功の鍵となっています。
生成AI活用の定着は、単なる技術導入ではなく、組織文化の変革プロジェクトです。今回紹介した5つのプロセスを参考に、あなたの会社でも生成AIを活用した業務効率化と競争力向上を実現してください。明日から始められる小さな一歩が、やがて大きな変革につながるはずです。
よくある質問(FAQ)
Q1 生成AI活用が企業で定着しない原因は何ですか?
多くの企業が生成AIツールを導入しても、全社的な活用に至らず、期待していた効果を得られていないのが現状です。これは、複雑なプロンプト作成のハードル、セキュリティへの不安、具体的な業務への適用イメージの不足などが原因として考えられます。
Q2 SHIFT社の「生成AI 360度」とはどのようなサービスですか?
SHIFT社の「生成AI 360度」は、全社的な生成AI活用を支援する包括的なサービスです。活用方針の策定からツール導入、社員教育、利用環境の構築、文化醸成までを一貫してサポートし、組織全体で生成AIが自然に使われる環境を作ることを目指します。
Q3 ノープロンプト生成AIツールとは何ですか?
ノープロンプト生成AIツールとは、複雑な指示文(プロンプト)を作成しなくても、簡単に生成AIを活用できるツールのことです。これにより、技術的な知識がない社員でも、すぐに業務で生成AIを利用できるようになり、学習コストの削減や品質の安定化に繋がります。
Q4 生成AIの利用率を向上させるために、どのようなKPIを設定すれば良いですか?
生成AIの利用率だけでなく、業務効率化時間、アウトプットの品質改善度合い、コスト削減効果、新規活用事例数など、多角的な指標を設定することが重要です。これらのKPIを定期的に測定することで、効果的な活用状況の把握と改善に繋がります。
Q5 生成AI活用を社内文化として根付かせるには、どのような取り組みが効果的ですか?
部門間で得られた成果や知見を共有する仕組みを作り、社内コミュニティやコンテストを通じて、生成AI活用を促進することが重要です。成功事例の共有、勉強会の開催、アイデア投稿プラットフォームの提供などを通じて、社員の自発的な参加を促し、学習文化を醸成します。
この記事の著者

池田朋弘(監修)
Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。
株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。











