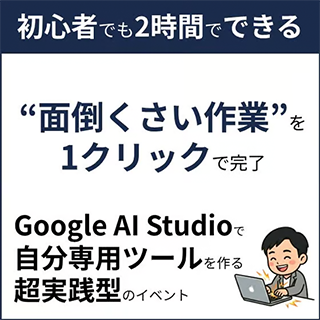再春館製薬のAI活用事例から学ぶ「個別最適化アプローチ」の実践方法
「AIを使って効率化を図る」という発想は、もはや当たり前になりました。しかし、ドモホルンリンクルで知られる再春館製薬所が取り組んでいるAI活用事例は、従来の効率化重視とは一線を画す興味深いアプローチを示しています。
それは、「顧客一人ひとりの心と体の状態に深く寄り添う個別最適化アプローチ」です。この考え方は、単なる自動化や大量処理を目的とするのではなく、むしろ人間らしい温かみのあるコミュニケーションをAIによって実現しようとする試みといえるでしょう。
本記事では、再春館製薬所の事例を詳しく分析し、この「個別最適化アプローチ」がなぜ注目に値するのか、そして他の業界や企業でも応用できる要素は何かを探っていきます。効率化だけではない、AIの新たな活用可能性を一緒に考えてみませんか。
目次
再春館製薬所が実現した「個別最適化アプローチ」とは

再春館製薬所のAI活用の核心は、効率化ではなく個々の顧客への深い理解と寄り添いにあります。同社は2025年7月にGROWTH VERSE社と共同で、AIを活用した個別最適化型顧客コミュニケーション基盤を導入しました。
具体的には、広告、メール、DM、アウトバウンドコールといった多様なチャネルにおいて、顧客の購買サイクルや購買履歴をAIが分析し、最適なタイミングと情報を届けることで顧客エンゲージメントの最大化と顧客満足度向上を図っています。
特に注目すべきは、この仕組みが「心地よさ」を重視した設計になっている点です。単に商品を売るためのタイミングを計算するのではなく、顧客にとって「今、この情報が欲しい」と感じられる瞬間を見極めることに重点を置いています。
従来の電話中心アプローチからの転換背景

再春館製薬所は長年、電話を中心とした顧客対応を行ってきました。注文や問い合わせ履歴、肌質や体の状態、ライフスタイルの変化などのカウンセリング情報を蓄積し、深い顧客理解を築いてきたのです。
しかし、時代の変化とともに電話からデジタルへと接点が移行し、一人ひとりの悩みの本質や背景を深く理解する機会が減少してしまいました。新規顧客の9割がデジタル経由で接点を持つ現状において、従来の電話中心のアプローチだけでは限界があったのです。
そこで同社は、AIを活用することで、デジタル接点でも従来の電話対応と同等かそれ以上の深い理解と寄り添いを実現しようと考えました。これは単なるデジタル化ではなく、「人間らしい温かみのあるコミュニケーションをデジタルでも実現する」という挑戦といえるでしょう。
AIが分析する購買サイクルと最適化の仕組み

再春館製薬所のAI活用の中核となるのが、購買サイクル分析です。AIが顧客の行動履歴を詳細に分析し、「購買確率」や「最適な購入サイクル」を算出します。
この分析結果に基づき、一人ひとりの「今」に寄り添う情報提供を行います。例えば、顧客の肌の状態や季節の変化、過去の購買パターンなどを総合的に判断し、「この時期にこの商品の情報をお届けすれば、お客様にとって最も価値のあるタイミングになる」という予測を立てるのです。
重要なのは、これが単なる売上最大化のためのタイミング計算ではないということです。顧客の「声なき声」を捉え、本当に必要とされる時期に、心に届く最適なタイミングで情報を提供することを目指しています。
多チャネル対応による具体的な成果

この個別最適化アプローチは、複数のコミュニケーションチャネルで実践されています。特に注目すべき成果が、メール施策での購買率約20%向上です。
従来の一斉配信型メールマーケティングとは異なり、AIが算出した購買サイクルを起点としたレコメンドメールを送信することで、この大幅な改善を実現しました。これは、顧客一人ひとりの状況に合わせたタイミングと内容の最適化がいかに効果的かを示す具体例といえるでしょう。
DMの場合も同様で、購買確率が高くなる時期に特化した情報を送付することで、従来の画一的なアプローチよりも高い効果を上げています。広告や架電においても、同じ考え方で最適化が図られています。
生成AI活用の可能性と現状の課題

この事例において生成AIがどの程度活用されているかは、現時点では明確に確認できていません。しかし、エイムスターなどのツールではLLMやマルチモーダルAIを用いた構造化レコメンドが明示されており、生成AIが活用されている可能性は高いと考えられます。
生成AIの活用により、限られたデータからでも「一人ひとりにこういう仮説があるから、こんな言い方をしたらいいのではないか」という個別の深い対応を営業担当者や電話担当者が想定できるようになります。これにより、担当者一人ひとりの対応精度を向上させることが可能になるのです。
効率化を超えた「担当者レベル向上」という新しい価値

この事例で特に興味深いのは、自動化や大量処理による効率化ではなく、一人ひとりの担当者のレベルを上げるという方向性です。
従来のAI活用では「いかに人の手を省くか」「いかに大量に処理するか」という効率化の観点が重視されがちでした。しかし、再春館製薬所のアプローチは、AIを使って担当者がより深く、より個別に顧客に寄り添えるようにサポートするという考え方です。
これにより、限られたデータでも顧客一人ひとりの状況を想定し、最適な対応を提供できるようになります。AIが人間の仕事を奪うのではなく、人間がより人間らしい、温かみのある対応ができるよう支援するという、理想的なAI活用の形といえるでしょう。
他業界への応用可能性と実践のヒント

この「個別最適化アプローチ」は、化粧品業界以外でも十分に応用可能です。例えば、教育現場では生徒一人ひとりの学習履歴とパフォーマンスデータをAIが分析し、個別最適な学習プランを提供する事例が既に存在します。
コンテンツマーケティング分野でも、The New York Timesが読者の心理状態と記事の感情要素をAIで分析し、ユーザーごとにパーソナライズしたコンテンツ配信で購読者維持率を13%向上させた事例があります。
重要なのは、効率化だけを目的とするのではなく、顧客や利用者一人ひとりの状況に深く寄り添うという基本姿勢です。AIの分析力を活用しながらも、最終的には人間らしい温かみのあるコミュニケーションを実現することが成功の鍵となります。
まとめ

再春館製薬所のAI活用事例は、従来の効率化重視のアプローチとは一線を画す、新しいAI活用の可能性を示しています。主なポイントを整理すると以下の通りです:
- 効率化ではなく個別最適化:顧客一人ひとりの心と体の状態に深く寄り添うアプローチを重視
- 購買サイクル分析の活用:AIが顧客の行動履歴を分析し、最適なタイミングと情報を算出
- 多チャネル対応:メール、DM、広告、電話など複数の接点で一貫した個別最適化を実現
- 担当者レベルの向上:自動化ではなく、人間がより深く顧客に寄り添えるようAIがサポート
- 他業界への応用可能性:教育、メディア、コンテンツマーケティングなど幅広い分野で活用可能
この事例から学べる最も重要な点は、AIを単なる効率化ツールとして捉えるのではなく、人間らしい温かみのあるコミュニケーションを実現するためのパートナーとして活用するという発想の転換です。あなたの業界や組織でも、この「個別最適化アプローチ」を参考に、顧客や利用者一人ひとりに深く寄り添うAI活用を検討してみてはいかがでしょうか。
参考リンク
本記事の内容は、以下の資料も参考にしています:
よくある質問(FAQ)
Q1 再春館製薬所のAI活用における「個別最適化アプローチ」とは何ですか?
顧客一人ひとりの心と体の状態に深く寄り添い、最適な情報を提供するアプローチです。単なる効率化ではなく、顧客にとって「今、この情報が欲しい」と感じられるタイミングを見極め、人間らしい温かみのあるコミュニケーションをAIによって実現しようとする試みです。
Q2 再春館製薬所はAIを使って顧客の購買サイクルをどのように分析しているのですか?
AIが顧客の行動履歴を詳細に分析し、「購買確率」や「最適な購入サイクル」を算出します。顧客の肌の状態や季節の変化、過去の購買パターンなどを総合的に判断し、最適なタイミングで情報提供を行うことで、顧客エンゲージメントの最大化と顧客満足度向上を図っています。
Q3 再春館製薬所がAIを活用したことで、どのような具体的な成果が出ていますか?
メール施策において購買率が約20%向上しました。これは、AIが算出した購買サイクルを起点としたレコメンドメールを送信することで実現しました。顧客一人ひとりの状況に合わせたタイミングと内容の最適化がいかに効果的かを示す具体例です。
Q4 再春館製薬所のAI活用事例から、他業界でも応用できることはありますか?
効率化だけでなく、顧客や利用者一人ひとりの状況に深く寄り添うという基本姿勢が重要です。AIの分析力を活用しながらも、最終的には人間らしい温かみのあるコミュニケーションを実現することが成功の鍵となります。教育現場やコンテンツマーケティング分野での事例も参考になります。
Q5 再春館製薬所がAI活用で重視している「心地よさ」とは具体的にどのようなことですか?
単に売上を最大化するためのタイミングを計算するのではなく、顧客にとって本当に価値のある情報を、適切なタイミングで提供するという姿勢です。顧客の「声なき声」を捉え、本当に必要とされる時期に、心に届く最適なタイミングで情報を提供することを目指しています。
この記事の著者

池田朋弘(監修)
Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。
株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。