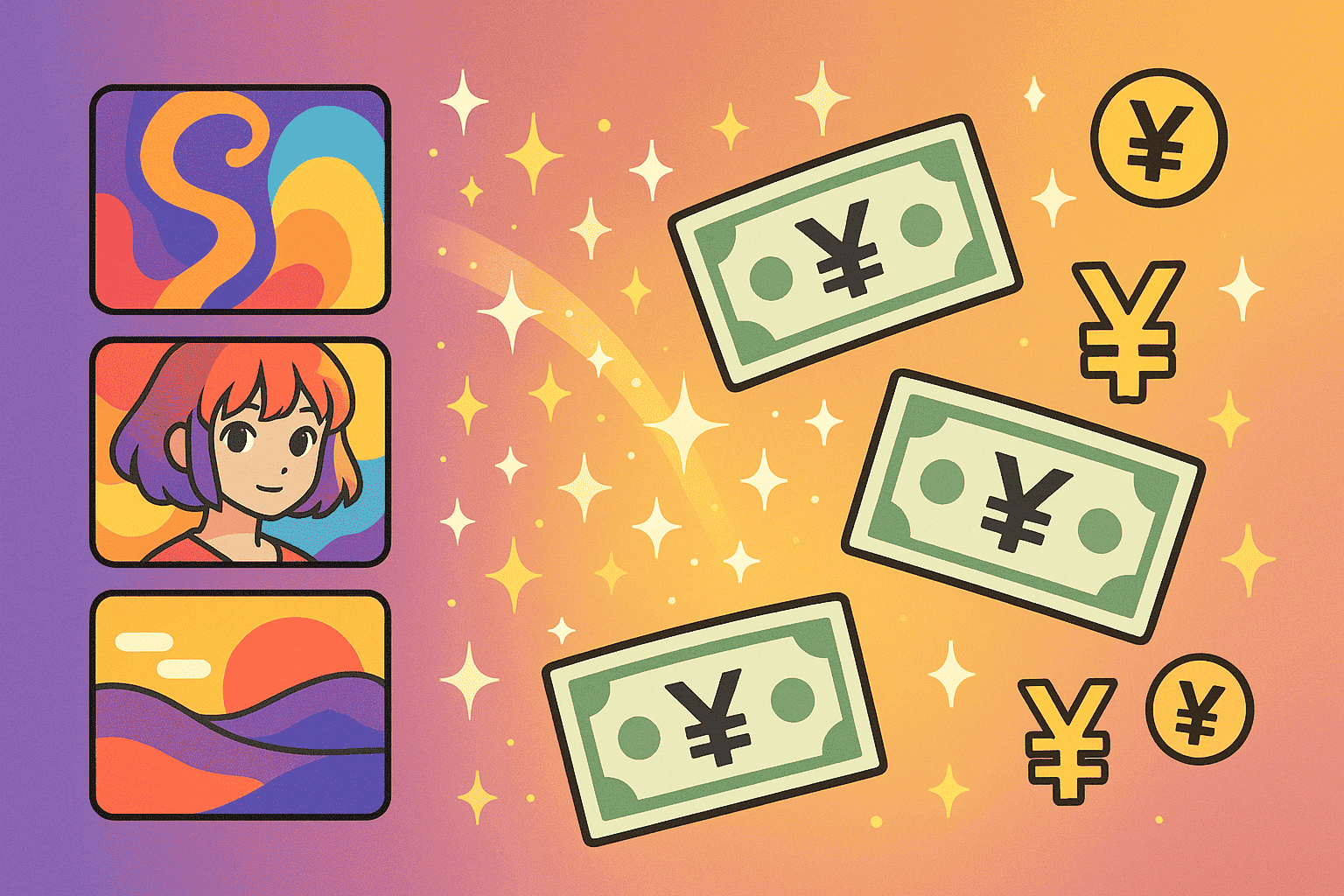ソフトバンク「Sarashina mini」API提供開始:国産LLMが切り拓く通信業界特化AIの新時代
ソフトバンクが国産大規模言語モデル(LLM)「Sarashina mini」のAPI提供を開始しました。この動きは、単なる新サービスの開始を超えて、日本の企業が海外製AIに依存することなく、安全で高品質なAIソリューションを活用できる新たな選択肢の誕生を意味します。
すでに通信業界向けの専用モデルも提供開始されており、他にも業界特化型AIの実用化が本格的に始まろうとしています。
私自身、以前からSarashinaシリーズには注目しており、オープンソース版をスマートフォンで試した際の印象は非常に良好でした。スマホで動く程度の小型モデルでありながら、処理速度が速く、実用性の高さを実感できたのです。今回API提供が開始されたSarashina miniは、その技術をさらに発展させた4600億パラメータの大規模モデルであり、企業での本格活用に向けた重要な一歩と言えるでしょう。
目次
Sarashina miniの技術的特徴と実用性

Sarashina miniは、ソフトバンクの子会社SB Intuitionsが開発した国産LLMです。4600億パラメータという大規模な構成でありながら、オンプレミス環境での運用が可能な設計となっています。これは、DGXSpark や高性能サーバーがあれば、企業が自社内で安全に運用できる規模感を意味します。
API提供される機能は主に以下の2つです:
- Chat Completion:対話形式でのAI応答機能
- Embedding:テキストの意味をベクトル化する機能
これらの機能により、企業は自社のシステムにAI機能を組み込み、カスタマーサポートの自動化や文書解析、社内ナレッジの活用など、幅広い用途での活用が可能になります。
通信業界特化モデルの戦略的意義

今回の発表で特に注目すべきは、通信業界向けの専用モデルが同時に提供開始されたことです。これは、Sarashinaをベースモデルとして、通信業界特有の専門知識や業務プロセスに特化したカスタマイズを施したモデルと考えられます。
通信業界では、ネットワーク設計、運用管理、障害対応など、高度な専門知識が求められる業務が多数存在します。汎用的なAIモデルでは対応が困難なこれらの領域に対して、業界特化型のAIモデルを提供することで、より実用的で価値の高いソリューションを実現できるのです。
実際、ソフトバンクの技術資料によると、同社は「Large Telecom Model」(LTM)という通信業界向けの生成AI基盤モデルを開発しており、これをSarashinaと統合することで、通信業界に特化した国産AIモデルを実現しています。
企業導入における実践的なアプローチ

Sarashina miniの導入形態は、従来のクラウドサービスとは異なるアプローチを取ると予想されます。一般的なAPI提供型のサービスではなく、契約ベースでの自社運用が中心になると考えられます。
この方式には以下のようなメリットがあります:
| セキュリティ | 機密データを外部に送信することなく、社内で完結した処理が可能 |
| カスタマイズ性 | 企業固有の業務プロセスや専門知識に合わせた調整が容易 |
| コスト効率 | 大量利用時のAPI課金を避け、固定コストでの運用が可能 |
| データ主権 | 日本国内でのデータ処理により、法的・規制的リスクを軽減 |
国産LLMの競争環境と差別化要因

日本国内では、NTTデータの「Tsuzumi」やNECの「Cotomi」など、複数の国産LLMが開発されています。これらのモデルも含め、国産AI(ソブリンAI)が、海外モデルとどのような差別化を図れるでしょうか。
私が考える主要な差別化要因は以下の通りです。
1. 日本語処理能力の高さ
Sarashinaは日本語に特化した学習を行っており、日本語の複雑な文脈や微妙なニュアンスを正確に理解できます。これは、日本企業での実用性を大きく左右する重要な要素です。
2. 安全な国内環境での実行
海外製のLLMを使用する場合、データが海外のサーバーに送信されるリスクがありますが、Sarashinaは完全に国内での処理が可能です。これにより、機密情報を扱う企業でも安心して利用できます。
3. 業界特化カスタマイズの柔軟性
通信業界向けモデルの提供開始が示すように、Sarashinaは特定業界のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。これにより、汎用モデルでは実現困難な、高度に専門化されたAIソリューションを提供できます。
企業での活用シナリオと期待される効果

Sarashina miniの企業での活用シナリオは多岐にわたります。特に以下のような用途での効果が期待されます:
カスタマーサポートの高度化
日本語の複雑な問い合わせに対して、文脈を正確に理解した適切な回答を生成できます。従来のチャットボットでは対応困難だった複雑な質問にも、人間に近いレベルで対応可能になります。
社内文書の活用促進
エンベッディング機能を活用することで、膨大な社内文書から関連情報を効率的に検索・抽出できます。これにより、ナレッジマネジメントの質が大幅に向上します。
業務プロセスの自動化
業界特化モデルを活用することで、専門的な判断が必要な業務プロセスの一部を自動化できます。例えば、通信業界では障害対応の初期判断や、ネットワーク設定の最適化提案などが可能になるでしょう。
ソブリンAIとしての戦略的価値

Sarashina miniの提供開始は、日本における「ソブリンAI」(主権AI)の実現に向けた重要な一歩です。これは、国家や企業が自国・自社の技術とデータを用いて、外部依存を最小限に抑えたAIシステムを構築する概念です。
海外製のAIサービスに依存することは、以下のようなリスクを伴います:
- 突然のサービス停止や利用制限
- データの海外流出リスク
- 外国の法律や規制の影響
- 技術的な独立性の喪失
Sarashina miniのような国産LLMの普及により、これらのリスクを軽減し、日本企業がより安全で持続可能なAI活用を実現できるようになります。
まとめ

ソフトバンクのSarashina mini API提供開始は、日本のAI業界における重要なマイルストーンです。以下の要点をまとめます:
- 技術的優位性:4600億パラメータの大規模モデルでありながら、オンプレミス運用が可能な実用的な設計
- 業界特化戦略:通信業界向け専用モデルの提供により、汎用AIでは実現困難な専門的なソリューションを実現
- セキュリティ重視:国内完結型の処理により、機密データを安全に扱える環境を提供
- ソブリンAIの実現:海外依存を減らし、技術的独立性を高める戦略的価値
- 市場への波及効果:国産AI市場の活性化と、他業界での業界特化AIの普及促進が期待される
今後、Sarashina miniがどのような企業で採用され、どのような成果を上げるかに注目していきたいと思います。国産LLMの実用化が本格化する中で、日本企業のAI活用がより安全で効率的なものになることを期待しています。
参考リンク
本記事の作成にあたり、以下の情報源も参考にしています:
- ソフトバンク プレスリリース(2025年11月5日)
- ソフトバンク プレスリリース(2025年10月29日)
- SoftBank Interview with Head of Homegrown Generative AI Development
- SoftBank Corp.’s Large Telecom Model—a Generative AI Foundation for the Telecom Industry
- LLM-jp Resources – Overview of Japanese LLMs
よくある質問(FAQ)
Q1 ソフトバンクのSarashina miniとは何ですか?
Sarashina miniは、ソフトバンクが開発した国産の大規模言語モデル(LLM)です。4600億パラメータを持ち、企業が自社環境で安全に運用できる設計になっています。APIを通じて、チャットコンプリーション(対話形式でのAI応答)とエンベッディング(テキストの意味をベクトル化)の機能が提供されます。
Q2 Sarashina mini APIで何ができますか?
Sarashina mini APIを利用することで、企業は自社のシステムにAI機能を組み込むことができます。例えば、カスタマーサポートの自動化、社内文書の検索効率向上、業務プロセスの自動化などが可能です。特に通信業界向けの専用モデルでは、ネットワーク設計や障害対応といった専門的な業務に特化した活用が期待できます。
Q3 Sarashina miniを導入するメリットは何ですか?
Sarashina miniを導入する主なメリットは、セキュリティの高さ、カスタマイズ性、コスト効率、そしてデータ主権の確保です。機密データを外部に送信せずに社内で処理できるため、情報漏洩のリスクを軽減できます。また、企業固有の業務プロセスに合わせて調整しやすく、大量利用時のAPI課金を避けて固定コストで運用できます。
Q4 Sarashina miniは他の国産LLMとどう違うのですか?
Sarashina miniは、特に日本語処理能力の高さ、安全な国内環境での実行、そして業界特化カスタマイズの柔軟性が特徴です。日本語の複雑なニュアンスを正確に理解し、国内サーバーで完結するため、海外製のLLMに比べて安心して利用できます。また、通信業界向けモデルのように、特定の業界ニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
Q5 Sarashina miniの導入にはどのような準備が必要ですか?
Sarashina miniを導入するには、まず4600億パラメータのモデルを運用できる高性能なGPUサーバー(DGXサーバーなど)が必要です。また、オンプレミス運用となるため、適切なアクセス制御や監査ログの管理体制など、セキュリティ体制の整備も重要です。段階的に導入し、効果を確認しながら拡大していくのがおすすめです。
この記事の著者

池田朋弘(監修)
Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。
株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。