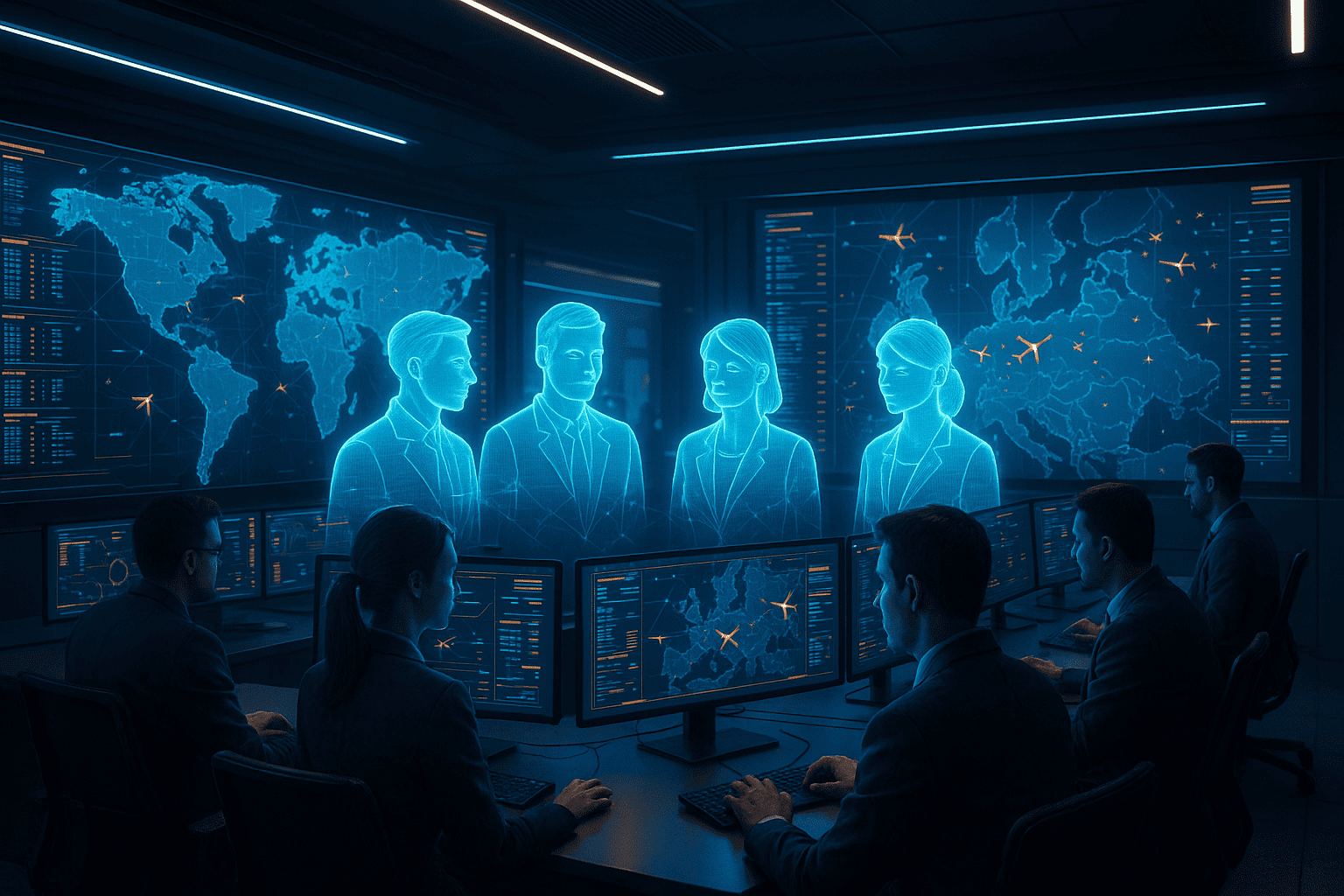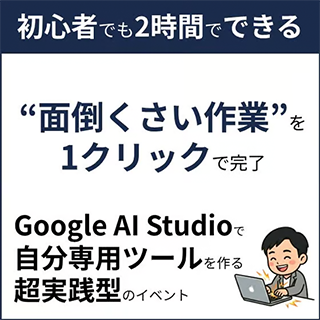AIエージェント活用の課題と解決策:振り力不足を克服する2つのアプローチ
AI技術の急速な進歩により、AIエージェントを活用した業務効率化への期待が高まっています。しかし、実際にAIエージェントを使いこなそうとすると、多くの人が同じ壁にぶつかります。それは「ある程度こちらが考えたり体制がないと、AIエージェントに振る力がまだない」という課題です。
私自身、最近プロダクト設計やツール開発に取り組む中で、この課題を痛感しています。開発作業をしようと思うと、どうしても家のパソコンに座って、カーソルなどのツールを開いて、ようやく頭が動き始める状態です。CursorのエージェントやClaude Code、Gemini CLIなどのツールを使いながら、自分がスタートしないとなかなかAIに相談することが難しいのが現状です。
理想的には、ある程度大きなタスクを振っておいて勝手にやってもらったり、SlackやウェブのUI上で「これこれこんなの先にやっといてね」と振っておいて、後で確認していけば、自分がその場にいない時間でもゴリゴリ進めることができるはずです。しかし、現在の私の力では、丸っと振ったときに返ってくるものを把握する自信もないし、外出先で思いついたときにそれをしっかりと依頼して渡せる能力がないのが実情です。
結果的に、猛烈に自分がボトルネックになって全然進まないケースが頻発しています。これは単に私のエンジニアリング能力や開発能力が不足しているだけでなく、作業の理解度が低いからできないという根本的な問題があると考えています。
目次
経験と理解度がAI活用の鍵を握る理由

一方で、資料作成やリサーチなどのホワイトカラー系のワークに関しては、外出中に指示を出すことも可能だと感じています。これは、もともと社長として何十人かに仕事を振ってきた経験があり、そちらの作業については理解度が高いからです。
つまり、作業の理解度が低いから、AIに適切に振ることができないのです。この課題感は何につながるかというと、結局かなり自分で前からやってきた仕事じゃないと中身のイメージが湧かないため、AIに振ろうと思ってもやっぱり振りにくいという状況を生み出します。
これは特に若手にとって深刻な問題です。あまり経験がない中でAIを使おうと思っても、やっぱりかなりしんどいという状況になってしまいます。若手をどう育てるのか問題にも直結する課題だと考えています。
私自身は幸いなことに、エンジニアリングはさておき、ホワイトカラーとしての仕事(コンサルティング、企業支援、事業作成など)に関しては相当経験を積んでいるため、理解度が高く、多分使いこなせる自信はあります。しかし、その部分を担う機会や経験する場がないと、やっぱりかなりきついのが現実です。
AI活用格差が生み出す深刻な生産性の差

この課題は、単なる個人的な悩みにとどまりません。これは結構重い課題として、いろんな人に影響を与えると考えています。具体的には、AIエージェントを使いこなせる人にめちゃくちゃ仕事が集まり、生産性が爆増する一方で、できない人の仕事が減っていき、価値の差がめちゃくちゃ増えるという状況が間違いなく起こっています。
実際に、2025年7月時点での調査結果を見ると、楽天グループでは要件定義書作成・プログラミング・テスト自動化をAIに委任することで、開発工数を最大80%削減した事例が報告されています。1週間かかっていた作業が2時間で完了するケースもあり、AI活用による生産性向上の効果は劇的です。
一方で、タクシー業界の分析では、需要予測AIの導入により低スキル乗務員の生産性が7%向上したものの、高スキル層への影響は限定的だったという興味深い結果も出ています。これは、AI活用によって従来の技術進歩が引き起こした「格差拡大」とは逆の効果(格差縮小)が示唆される一方で、AI活用スキル自体が新たな格差要因になる可能性を示しています。
私自身、エンジニア能力として別に勝負はしないわけですが、とは言っても自分が思ったこともできないし、自動化もできないし、仕組み化もできないのでは困ります。やはりAIに振ってタスクを進めるためには、仕事の中身を知ったり、仕事のイメージがないと簡単ではないというのが現在の課題感です。
課題解決に向けた2つのアプローチ戦略

この課題に向けて、私は大きく二つの可能性があると考えています。
アプローチ1:スキル向上による理解度の深化
一つ目は、自分自身がカーソルを使ったりしながら、ある程度開発の経験を積んで、中身のスキルを高めることによって振りやすくなっていくという方向性です。
これは従来のOJT(On-the-Job Training)と同様の考え方で、やる内容の理解を高めて、自分自身もそれなりの中身が分かってくる、設計構造が分かっていれば振りやすくなるという、経験による成長アプローチです。
具体的には、カーソルなどのAI支援開発ツールを使いながら実際に手を動かし、プログラミングの基本的な流れや構造を理解していくことで、AIエージェントに対してより具体的で適切な指示を出せるようになることを目指します。
アプローチ2:振り慣れによる実践力の向上
もう一つは、中身は知らなくていいから、ばんばん振っていくということに慣れた結果として、中身分からなくても結構振ることができて何とかなるという方向性です。
これは、技術的な詳細を完全に理解しなくても、AIエージェントとのやり取りのパターンや、効果的な指示の出し方、結果の検証方法などを経験的に身につけることで、実用的なレベルでAIを活用できるようになるというアプローチです。
2025年7月時点では、PromptFlow(Azure)のGUIベースシステムなど、コード未経験者でもチーム単位での運用が可能なツールが登場しています。プロンプトの作成・実行・ABテスト・改善をPDCAサイクルで自動化し、議事録要約や構造設計などのタスクをプロンプト1つで処理可能なケースが報告されており、このアプローチの実現可能性を示しています。
相乗効果による精度向上
これらの二つのアプローチは、どちらか一つを選ぶというよりは、両方とも相乗効果でマシになっていく、精度が上がっていくと考えています。
スキル向上により理解度が深まれば、より適切な指示を出せるようになり、同時に振り慣れることで実践的なノウハウが蓄積されます。この二つが組み合わさることで、AIエージェント活用の精度と効率が飛躍的に向上すると期待しています。
エンジニア領域からホワイトカラー全般への展開

現在、プログラミングやエンジニア領域がAIエージェントを活用する最も重要な部分となっていますが、これはホワイトカラーの仕事全般に入ってくることは間違いないと考えています。
今エンジニア系のエージェントで積んでいる経験が、確実にホワイトカラーの領域にも応用され、ホワイトカラーの業務理解度が上がることで、多分相当振りやすくなり、より精度や可能性を広げていくような方向性になるのではないかという仮説を持っています。
また、従来のプロンプト設計から、データ・検索・ツールの統合設計へパラダイムが移行しており、自動ナレッジ選択システムなど、ユーザーの質問内容に応じて適切な情報源を自動選択する仕組みも実装され始めています。
まとめ:新しい時代の働き方への適応

AIエージェント活用における現在の課題は、技術的な問題というよりも、人間側の理解度と経験不足に起因するところが大きいと考えています。この課題を解決するためには:
- スキル向上アプローチ:実際に手を動かして作業の中身を理解し、適切な指示を出せるようになる
- 実践慣れアプローチ:技術詳細を完全理解しなくても、効果的なやり取りパターンを身につける
- 相乗効果の活用:両アプローチを組み合わせることで、AIエージェント活用の精度と効率を飛躍的に向上させる
- 継続的な学習:エンジニア領域での経験をホワイトカラー業務全般に応用し、活用範囲を拡大する
AI活用力で生産性に大きな差がつくことは自明であり、早めにモードチェンジすることが重要です。皆さんもぜひ、AIエージェントへの仕事の振り方やトレーニング方法について、経験や工夫を共有していただければと思います。この新しい時代の働き方における重要なインプットとして、お互いに学び合いながら成長していきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1
AIエージェントに仕事を振れない原因は何ですか?
AIエージェントにタスクを指示できない主な原因は、タスク内容に対する理解不足です。作業内容の理解が浅いと、AIに適切な指示が出せず、期待する結果を得られないため、AIエージェントを十分に活用できません。
Q2
AIエージェント活用で生産性を向上させるにはどうすればいいですか?
AIエージェント活用で生産性を高めるには、自身のスキル向上とAIへの指示に慣れることが重要です。タスク内容の理解を深めつつ、AIエージェントに積極的にタスクを振ることで、AI活用スキルが向上し、生産性向上につながります。
Q3
AIエージェントを使いこなせる人とそうでない人で、どのような差が生まれますか?
AIエージェントを使いこなせる人は、業務効率が大幅に向上し、生産性が飛躍的に向上します。一方、使いこなせない人は、AIの恩恵を受けられず、生産性の差が拡大する可能性があります。この差は、個人のスキルや経験だけでなく、組織全体のAI活用能力にも影響します。
Q4
AIエージェント活用スキルを向上させるための2つのアプローチは何ですか?
AIエージェント活用スキル向上のためのアプローチは2つあります。1つは、実際に手を動かして開発経験を積み、タスク内容への理解を深めること。もう1つは、タスクの中身を深く理解していなくても、AIにタスクを振ることに慣れることです。両方のアプローチを組み合わせることで、AI活用スキルを効率的に向上できます。
Q5
AIエージェントの活用は、今後どのように広がっていくと予想されますか?
AIエージェントの活用は、現在主流のプログラミングやエンジニアリング領域から、資料作成やリサーチといったホワイトカラー業務全般へと拡大していくと予想されます。業務理解度が深まることで、AIエージェントへの指示が容易になり、より広範な業務でAIを活用できるようになります。
この記事の著者

池田朋弘(監修)
Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。
株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、
AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、
チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。