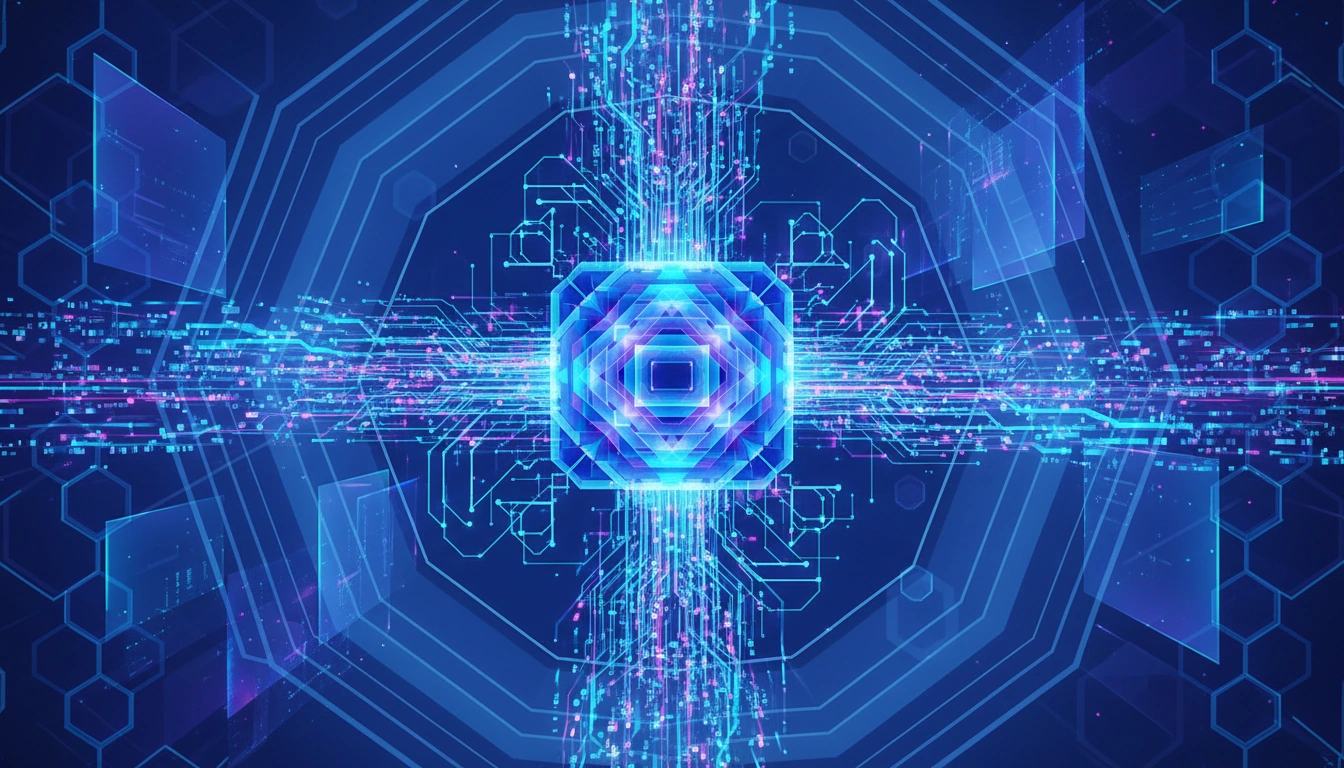NotebookLMレポート機能が大進化!8種類の形式から選択可能で自由度が飛躍的に向上
GoogleのAIノートアプリ「NotebookLM」のレポート機能が、2025年9月のアップデートで劇的な進化を遂げました。従来の決められた形式のレポート生成から、ソースの内容や目的に合わせた多様な形式のレポート生成が可能となり、コンテンツ制作の効率が大幅に向上しています。
この進化により、研究者、学生、ビジネスパーソンなど、様々な立場の方が自分のニーズに合わせたレポートを簡単に作成できるようになりました。特に注目すべきは、AIが自動的に最適なレポート形式を提案してくれる機能と、完全にカスタマイズ可能な独自レポート作成機能です。
目次
NotebookLMレポート機能の全体像

NotebookLMのレポート機能は現在、計8種類のフォーマットから選択可能となっています。これらは大きく2つのカテゴリーに分類されます:
- 固定の4つの基本形式:従来から提供されている定型フォーマット
- 動的な4つの提案形式:AIがソースの内容に応じて自動提案するカスタマイズフォーマット
この構成により、ユーザーは自分の目的や用途に応じて、最適なレポート形式を選択できるようになりました。従来の箇条書き要約とは異なり、読みやすい文章構造でアウトプットされるのが大きな特徴です。
固定の4つの基本レポート形式
まず、従来から提供されている基本的な4つのレポート形式について詳しく見ていきましょう。
1. 概要説明資料(Summary)
重要な分析情報と引用を含む包括的なソース概要を生成します。アップロードした資料の要点を整理し、引用元も明確に示してくれるため、学術的な用途や業務報告に最適です。
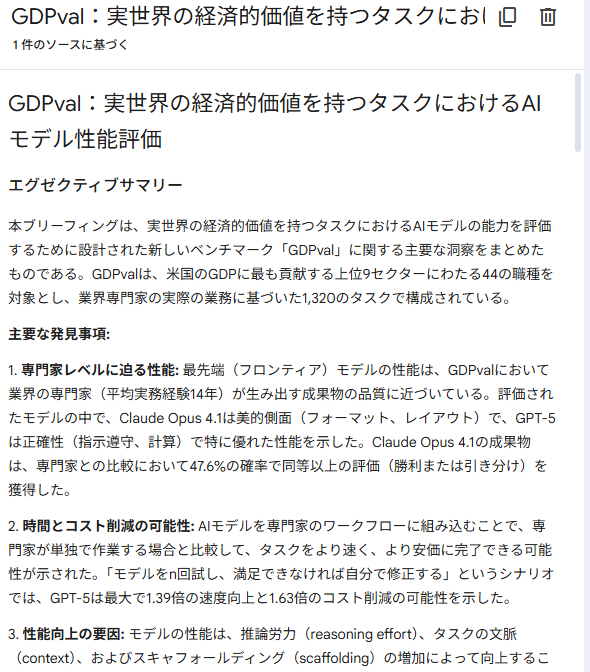
2. 学習ガイド(Study Guide)
学習に最適化されたコンテンツを作成する形式です。小テスト、推奨エッセイ問題、主要な用語集などを自動生成し、教育現場や自己学習において非常に有効です。質問と答えの形式で構成され、理解度を確認しながら学習を進められます。
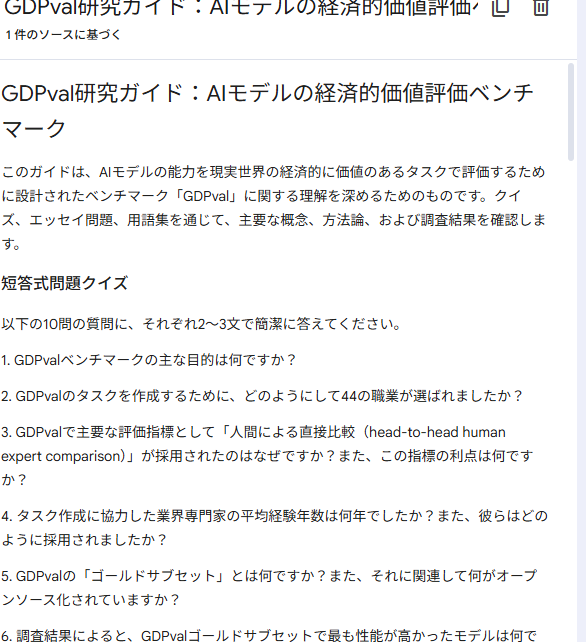
3. 独自に作成(Custom)
最も自由度の高い形式として提供されている機能です。構造やスタイル、トーンなどを自分で細かく指示して、完全にオリジナルのレポートを作成できます。この機能により、ユーザーは自分の具体的なニーズに合わせて、カスタマイズされたレポートを生成することが可能です。
4. ブログ投稿(Blog Post)
指定したソースをもとに、ブログ記事形式でレポートを自動生成する新機能です。読みやすい文章構造で、一般読者にも理解しやすい形式でコンテンツを作成してくれます。文章のフォーマットが柔らかく、従来の硬い報告書とは異なる親しみやすい文体で情報を伝えることができます。
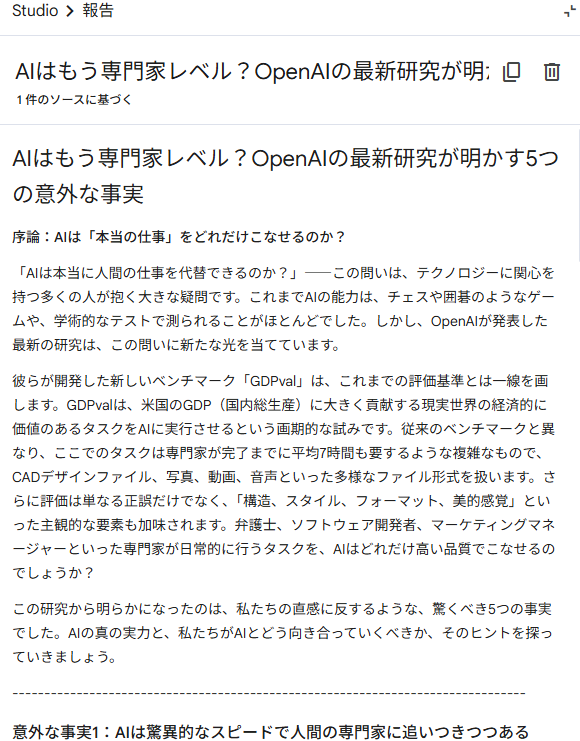
AIによる動的な4つの提案形式
NotebookLMの最も革新的な機能の一つが、AIがソースの内容を分析して自動的に最適なレポート形式を提案してくれる機能です。この機能により、ユーザーはプロンプト作成に悩むことなく、効率的にレポート生成を開始できます。
コンテンツに応じた自動提案の仕組み
AIは、アップロードされた資料のテーマや業界を自動的に識別し、それに応じて生成するレポート形式を推奨してくれます。例えば:
- 経済理論に関する学術論文をアップロードした場合:「主要用語の用語集」や「論文の示唆を解説する雑誌風記事」を提案
- 短編小説の草稿をアップロードした場合:「登場人物の分析」や「プロットの詳細な批評」を提案
- 技術文書の場合:「テクノロジー紹介」や「競合分析」などの形式を提案
提案される主な形式例
実際に提案される形式には以下のようなものがあります:
| 形式名 | 用途 | 特徴 |
| 包括的分析(Comprehensive Analysis) | 詳細な分析レポート | 多角的な視点からの深い分析 |
| テクノロジー紹介(Technology Introduction) | 技術解説・提案書 | 技術的内容を分かりやすく説明 |
| 提案書(Proposal) | 企画・提案資料 | 説得力のある提案形式 |
| 解説記事(Explanatory Article) | 一般向け解説 | 専門知識を平易に解説 |
ブログ記事形式の革新性
新しく追加されたブログ記事形式は、従来のレポート機能とは一線を画す革新的な機能です。この形式の最大の特徴は、読みやすさと親しみやすさにあります。
読みやすさの向上
ブログ記事形式では、硬い報告書調ではなく、読者にとって理解しやすい文章構造でコンテンツが生成されます。専門的な内容であっても、一般読者が理解できるような平易な表現で説明してくれるため、幅広い読者層に対応できます。
柔らかい文章フォーマット
従来の箇条書きや硬い文体とは異なり、自然な文章の流れで情報を整理してくれます。これにより、読者の関心を引きつけながら、重要な情報を効果的に伝えることができます。
レポート機能の実践的な活用方法
NotebookLMのレポート機能を効果的に活用するためには、目的に応じた形式選択が重要です。以下に、具体的な活用シーンをご紹介します。
学術・研究用途
- 概要説明資料:論文の要約や研究報告書の作成
- 学習ガイド:試験対策や知識の整理
- 包括的分析:複数の資料を横断した詳細分析
ビジネス用途
- 提案書:企画書や営業資料の作成
- テクノロジー紹介:新技術の社内説明資料
- 競合分析:市場調査レポート
コンテンツ制作用途
- ブログ記事:Webコンテンツの作成
- 解説記事:専門知識の一般向け解説
- 独自に作成:特定の要件に合わせたカスタムコンテンツ
まとめ
NotebookLMのレポート機能の進化は、コンテンツ制作と情報整理の分野において革新的な変化をもたらしています。主なポイントを以下にまとめます:
- 8種類の多様なレポート形式:固定の4つの基本形式と、AIが提案する4つの動的形式から選択可能
- ブログ記事形式の追加:読みやすく親しみやすい文章構造でのコンテンツ生成が可能
- AIによる自動提案機能:ソースの内容に応じて最適なレポート形式を動的に提案
- 完全カスタマイズ機能:独自に作成機能により、構造からスタイルまで自由に指定可能
- 効率的な情報処理:多様な入力形式に対応し、一括処理による大幅な時間短縮を実現
これらの機能により、研究者、学生、ビジネスパーソン、コンテンツクリエイターなど、様々な立場の方が自分のニーズに合わせた高品質なレポートを効率的に作成できるようになりました。NotebookLMは今後も継続的な進化を続け、さらに便利で実用的なツールとして発展していくことが期待されます。
よくある質問(FAQ)
Q1 NotebookLMのレポート機能では、どのような形式のレポートが作成できますか?
NotebookLMのレポート機能では、大きく分けて固定の4つの基本形式(概要説明資料、学習ガイド、独自に作成、ブログ投稿)と、AIがソースの内容に応じて提案する4つの動的な形式(包括的分析、テクノロジー紹介、提案書、解説記事)の計8種類のレポートを作成できます。
Q2 NotebookLMのブログ記事形式のレポートは、従来のレポートと何が違いますか?
NotebookLMのブログ記事形式のレポートは、従来の硬い報告書調のレポートとは異なり、読者にとって理解しやすい文章構造でコンテンツが生成されます。専門的な内容でも一般読者が理解できるような平易な表現で説明されるため、読みやすく親しみやすいのが特徴です。
Q3 NotebookLMのレポート機能で、AIが自動でレポート形式を提案してくれるのはどのような場合ですか?
NotebookLMでは、アップロードされた資料のテーマや業界をAIが自動的に識別し、それに応じて最適なレポート形式を推奨してくれます。例えば、経済理論に関する学術論文をアップロードした場合、「主要用語の用語集」や「論文の示唆を解説する雑誌風記事」などが提案されます。
Q4 NotebookLMのレポート機能は、ChatGPTなどの他のAIツールと比べて何が優れていますか?
NotebookLMは、アップロードした資料を「ノートブック」として管理し、それらの資料に基づいてレポートを生成するため、情報の出典が明確で信頼性の高いレポートを作成できます。また、PDFやYouTube動画など多様な入力形式に対応し、レポート作成に特化した機能設計により、実用的で構造化されたアウトプットを得られます。
Q5 NotebookLMのレポート機能を活用することで、どのようなメリットがありますか?
NotebookLMのレポート機能を活用することで、情報収集とリサーチの効率が大幅に向上します。テーマに沿った記事、論文、動画などを一括してアップロードし、AIが自動的に内容を分析・整理してくれるため、手作業での情報整理が不要になり、作業時間を大幅に短縮できます。
この記事の著者

池田朋弘(監修)
Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。
株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。