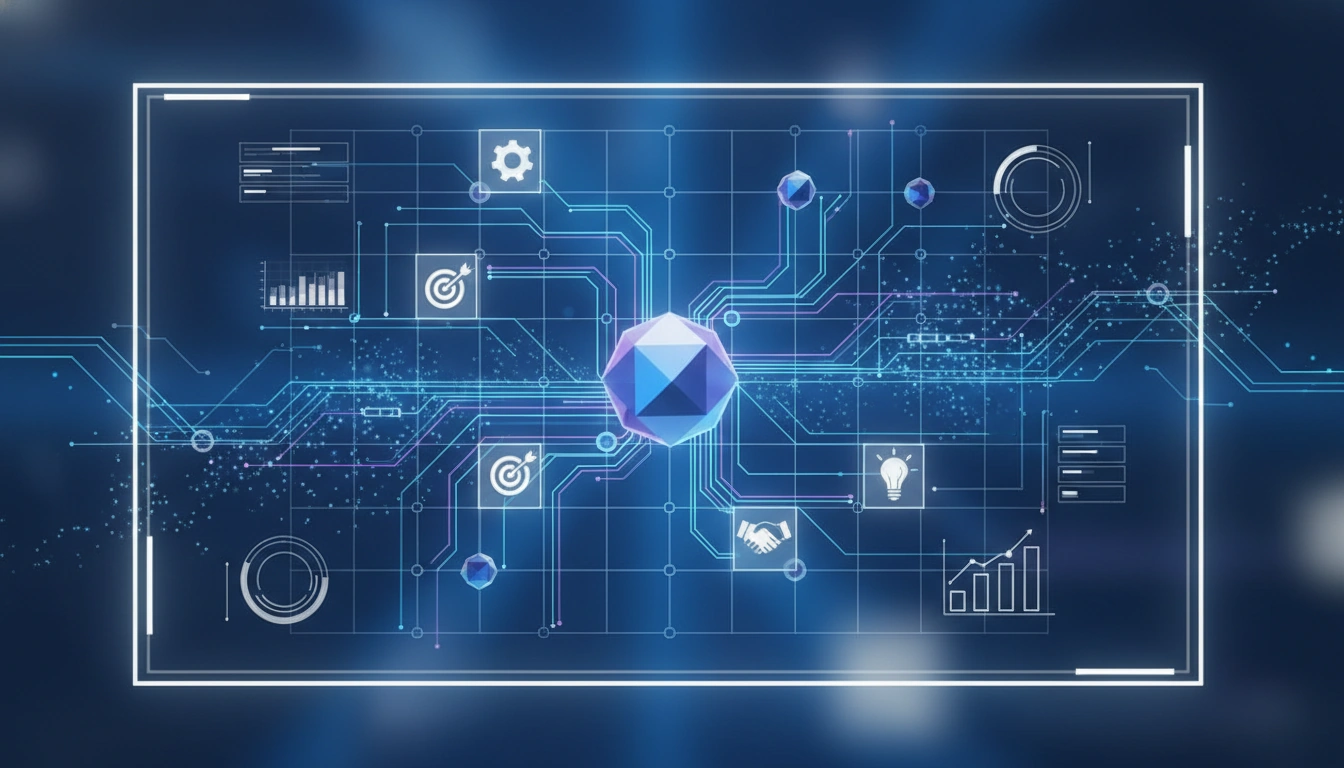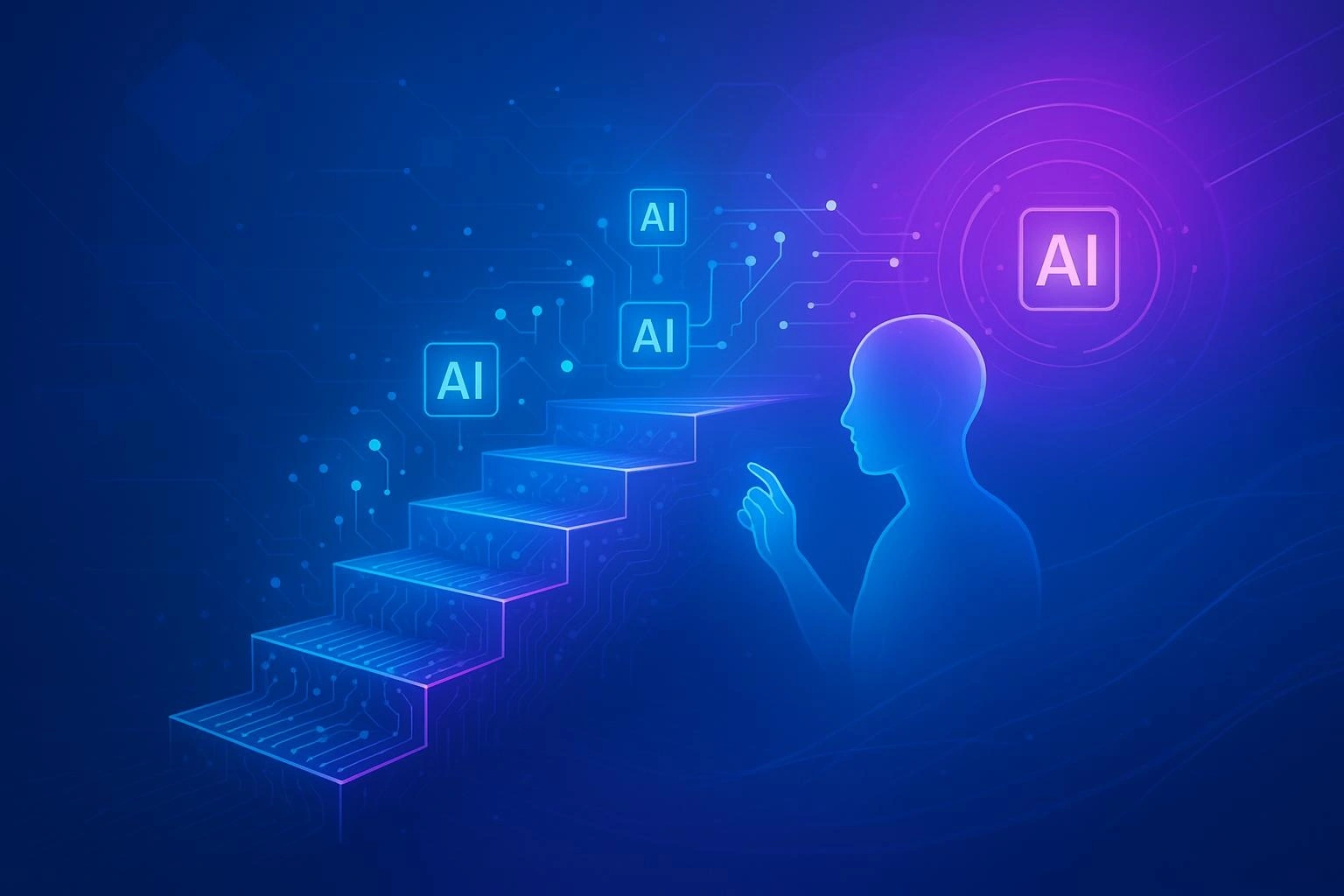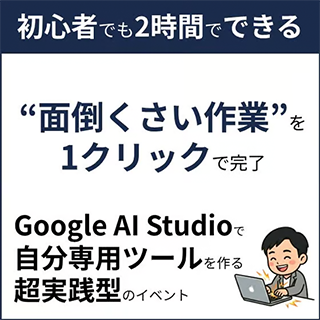NTTデータ×テプコカスタマーサービス事例に学ぶ、営業AI活用の現実と実践ポイント
営業活動におけるAI活用は、もはや「検討すべき選択肢」ではなく「競争力維持のための必須要素」となりつつあります。しかし、多くの企業が「AIを導入すれば営業が劇的に改善される」という期待を抱く一方で、実際の導入においては様々な課題に直面しているのが現実です。
今回は、NTTデータとテプコカスタマーサービスが共同で実施した営業AI活用事例を詳しく分析し、太陽光発電事業における営業プロセスの効率化がどのように実現されたのか、そして私たちが学ぶべき実践的なポイントについて解説します。この事例は、限られた人的リソースで全国展開を図る企業にとって、非常に参考になる内容となっています。
目次
テプコカスタマーサービスが直面していた営業課題

テプコカスタマーサービスは太陽光設備サービス事業をメインとする企業で、全国各地に顧客を抱えながらも、人的リソースが限られているという典型的な課題を抱えていました。
同社の営業プロセスは、大きく3つのステップで構成されていました。まず、優先するターゲットセグメントを確認し、続いてメール送信やDMで架電を行い営業にトスアップ、最後に営業担当者が全国各地に足を運んで提案を行うという流れです。
この従来のアプローチには、以下のような具体的な課題がありました:
- ターゲット選定の非効率性:仕分け作業に膨大な時間がかかっていた
- インサイドセールスの限界:他社にも同様の営業担当者がいる中で、担当者になかなかつながらない
- 営業人員不足:全国展開に対して営業人員が圧倒的に不足していた
これらの課題を解決するため、効率化と精度向上によるターゲティング向上、そして早期フェーズから現場の顧客接点を強化することが急務となっていました。
3つの柱で構成されたAI活用戦略

NTTデータとテプコカスタマーサービスは、営業プロセスの各段階にAIを導入する包括的な戦略を策定しました。この戦略は以下の3つの柱で構成されています:
| 活用領域 | 具体的な施策 | 期待効果 |
| 商談化・受注 | 提案書・スクリプトの自動作成 | 提案品質の向上と作業時間短縮 |
| ターゲット選定 | 建物情報の自動検出 | リード発掘精度の向上 |
| アプローチ | インサイドセールス代行 | 架電効率の向上と人的リソース最適化 |
それぞれの施策について、量と質の両面で価値を提供することを目指しており、単なる作業の自動化ではなく、営業活動全体の質的向上を図っています。
提案書自動作成:テンプレートとAIの絶妙な組み合わせ

提案書作成の自動化は、この事例の中でも特に注目すべき成果を上げた領域です。従来、慣れた営業社員でも提案書作成に2時間半を要していましたが、AIの導入により大幅な効率化を実現しました。
3段階の提案プロセスとAI活用
提案書作成プロセスは、顧客との関係性に応じて3つの段階に分けられています:
- 初回訪問前:顧客情報がほとんど入手できない段階でのテンプレート通りの提案書を活用
- 初回訪問後:会議で得られた情報をPowerPointアドインに入力し、提案書を自動更新
- ニーズ確認後:社内の訪問履歴、商談結果、見積もり情報を基にプログラムで費用算出するとともに、合意内容を踏まえた提案書の流れ替えを実施
重要なのは、AIが「丸っと作らせる」のではなく、既存のテンプレートの中身を一部AIで書き換えていくアプローチを採用している点です。これにより、ブランドの一貫性を保ちながら、個別の顧客ニーズに対応した提案書を効率的に作成できています。
PowerPointアドインという現実的な選択
提案書作成ツールとして、PowerPoint上のアドインツールを採用したのは非常に現実的な判断でした。PowerPointは営業現場で必ず使用されるツールであり、新しいシステムを覚える必要がないため、導入時の抵抗を最小限に抑えることができます。また、生成AIよりもテンプレートに沿ったミスのない資料が作成できます。
アクセンチュアさんの提案書作成においても同様にPowerPointアドインを活用しているようです。
検証の結果、グラフや表の表現も含めて、テンプレート10ページが高い精度で実現できており、2回目訪問時の訴求力向上の可能性も確認されているようです。
建物情報調査の自動化:効率化は実現、精度向上は課題
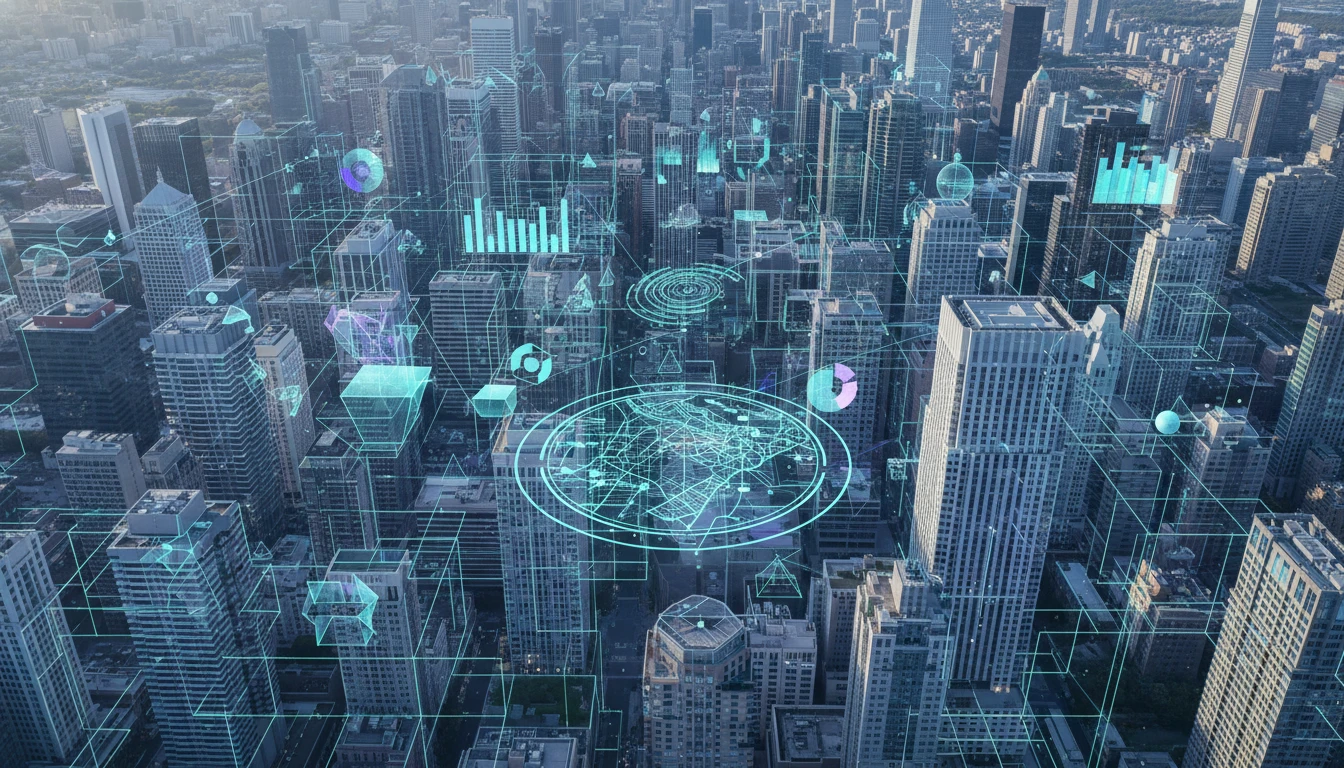
リード発掘の精度向上を目指した建物情報調査の自動化では、独自の航空写真と2D・3D解析可能なツールを活用して、条件に合致する建物を自動検出する取り組みが行われました。
従来は1件ずつGoogleマップで確認する作業に毎月120時間程度を要していましたが、この自動化により大幅な作業時間削減を実現できる可能性があるとのことです。1人あたり月1000件程度の確認作業を効率化できたことは、人的リソースの有効活用という観点で大きな成果といえます。
一方で、有望リード発掘の精度向上については、明確な成果確認が困難だったという課題も明らかになりました。しかし、自動化による調査稼働削減や、より網羅的な調査ポテンシャルの向上効果は確認されており、将来的な改善の余地があると考えられます。
この取り組みは生成AIだけでは難しく、複数のデータソースや技術を活用する必要があるため、多くの会社がすぐに実行するのは難しいと思いますが、参考になります。
インサイドセールス代行:技術的可能性と現実的課題

架電用のAIエージェントによるインサイドセールス代行は、技術的には一定の成果を示しました。検証担当者からは「(会話が)想像していたよりも自然だった」という評価を得ており、ある程度柔軟なシナリオ対応も可能であることが確認されています。
しかし、この領域については慎重な検討が必要です。AIが電話をかけてくることに対する顧客の印象や、実証実験段階であることを考慮すると、現時点では限定的な活用に留めるのが現実的でしょう。
むしろ、架電は人間が行い、スクリプトをAIが作成するというアプローチの方が、顧客体験と効率化のバランスを取りやすいと考えられます。また、架電ではなくメールやDMといったチャネルでのAI活用の方が、現段階では実用性が高いかもしれません。
実践的な導入ポイントと優先順位
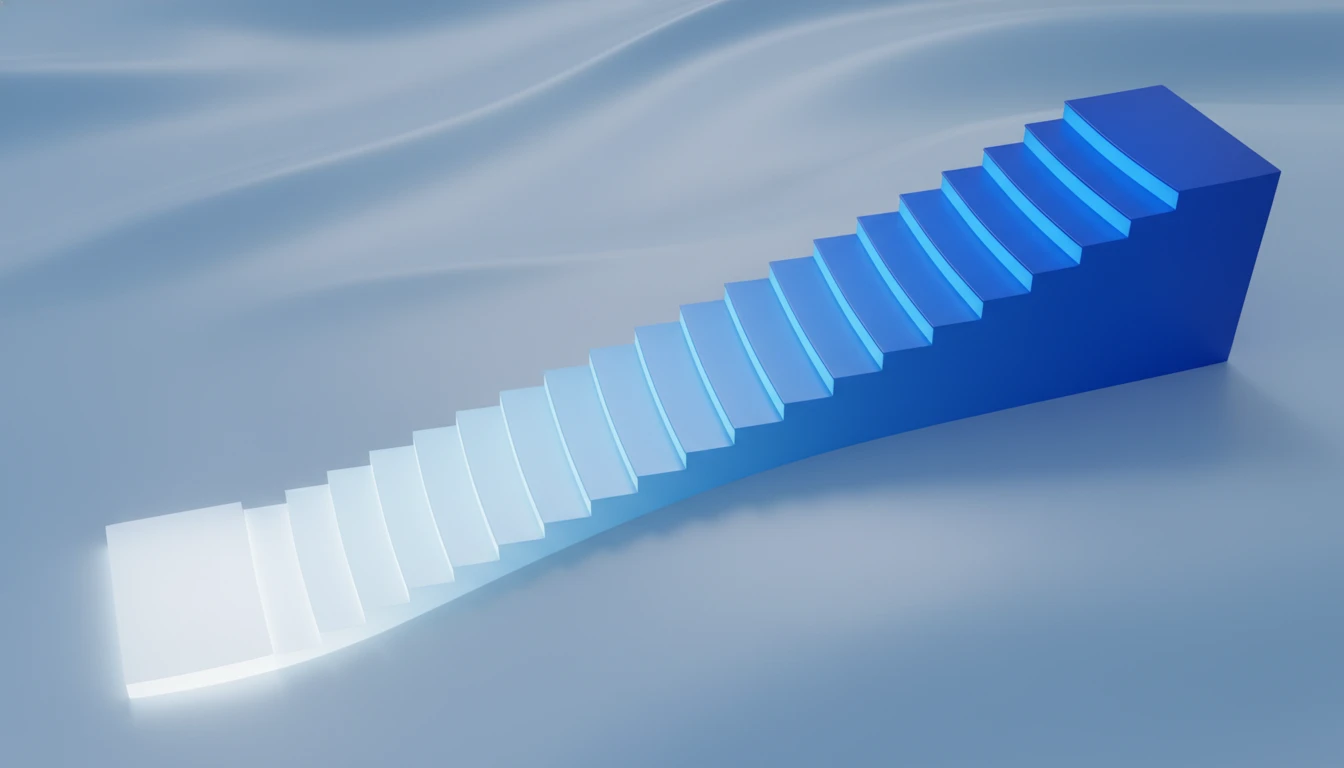
この事例から学べる実践的なポイントを整理すると、以下のような優先順位で検討することをお勧めします:
最優先:提案書作成の自動化
3つの施策の中で最も実現しやすく、即効性が期待できるのが提案書作成の自動化です。既存のテンプレートを活用し、PowerPointアドインのような使い慣れたツール上で実装することで、導入時の抵抗を最小限に抑えながら効果を実現できます。
PowerPoint AdWinの開発もViveコーディングを活用することでそこまで大きなリソースをかけずに実現することができます。実際に私が作成した「いけとも式Powerpointマクロ」などもぜひ参考にしてください。
特に重要なのは、基礎数値や経済性計算など、明らかにロジックが決まっていてミスが許されない部分を別のプログラムで自動化することです。これにより、人的ミスを防ぎながら、営業担当者はより戦略的な部分に集中できるようになります。
次の段階:アプローチ手法の改善
架電代行よりも、メールやDMといったチャネルでのAI活用から始めることをお勧めします。架電スクリプトの自動生成や、顧客セグメントに応じたメッセージのパーソナライゼーションなど、人間が最終的な判断を行う前提でのAI活用が現実的です。
長期的課題:ターゲット選定の高度化
ターゲット選定の自動化は、生成AIというよりも、より専門的なロジックや機械学習アルゴリズムが必要な領域です。短期間での実現は困難ですが、必要な情報を収集し、優先度をつけるロジックを段階的に構築していくことで、中長期的な効果が期待できます。
規模感と予算に応じた導入戦略

この事例は、規模感のある営業組織や、少数精鋭でも一定の予算がある事業において、AI活用の可能性を示しています。しかし、すべての企業が同じレベルの投資を行う必要はありません。
特に提案書作成に関しては、PowerPointアドインやマクロのような比較的簡単に作成できるツールを活用することで、コストをかけずにスモールスタートすることが可能です。まずは小規模な実証実験から始めて、効果を確認しながら段階的に拡大していくアプローチが現実的でしょう。
AI活用成功のための重要な考慮事項

営業AIの導入を成功させるためには、技術的な側面だけでなく、組織的な準備も重要です。
データ品質の確保
AIの効果は、投入するデータの品質に大きく依存します。CRMに登録された情報の精度向上や、過去の提案書・商談結果の体系的な整理など、データ基盤の整備が前提となります。
段階的な導入と継続的な改善
一度にすべてを自動化しようとするのではなく、効果が見込める部分から段階的に導入し、継続的に改善を重ねることが重要です。特に営業プロセスは企業ごとに異なるため、自社の実情に合わせたカスタマイズが必要になります。
営業チームの理解と協力
AIツールの導入成功には、営業チームの理解と協力が不可欠です。「AIに仕事を奪われる」という不安ではなく、「AIを活用してより価値の高い仕事に集中できる」という前向きな認識を共有することが重要です。
まとめ:営業AI活用の現実的なロードマップ
NTTデータとテプコカスタマーサービスの事例は、営業AI活用の現実的な可能性と課題を明確に示しています。重要なのは、以下のポイントを押さえた段階的なアプローチです:
- 提案書作成の自動化から開始:最も実現しやすく、即効性が期待できる領域
- 既存ツールとの連携を重視:PowerPointアドインのような使い慣れたツール上での実装
- 完全自動化ではなく人間との協働:AIが下書きを作成し、人間が最終判断を行う仕組み
- データ品質の継続的な改善:AIの効果を最大化するための基盤整備
- 段階的な拡大:小規模な実証実験から始めて、効果を確認しながら拡大
営業AI活用は、決して「魔法の杖」ではありません。しかし、適切な戦略と段階的な導入により、限られたリソースで営業効率を大幅に向上させることは十分可能です。この事例を参考に、自社の営業プロセスにおけるAI活用の可能性を検討してみてはいかがでしょうか。
参考リンク
本記事の内容は、以下の資料も参考にしています:
- NTTデータ データインサイト
- Sales Proposal Generation AI Market Research Report 2033
- AI Is Transforming Productivity, but Sales Remains a New Frontier – Bain Technology Report 2025
よくある質問(FAQ)
Q1 営業AIで提案書を自動作成するメリットは何ですか?
提案書作成を自動化することで、営業担当者の作業時間を大幅に短縮できます。事例では、従来2時間半かかっていた作業が効率化されました。また、ロジックが固定されている基礎数値や経済性計算などを自動化することで、人的ミスを減らし、提案品質の向上にもつながります。
Q2 営業AIを導入する際、提案書作成以外に優先すべきことは何ですか?
提案書作成の自動化が最も取り組みやすく、効果も期待できます。次に、メールやDMなど、顧客へのアプローチ手法を改善することも重要です。AIを活用して架電スクリプトを自動生成したり、顧客セグメントに合わせてメッセージをパーソナライズしたりすることで、効率的な営業活動が可能です。
Q3 営業AIの導入で、インサイドセールスはどのように変わりますか?
AIエージェントによるインサイドセールス代行は、技術的には可能ですが、顧客の印象を考慮すると慎重な検討が必要です。現段階では、AIに架電スクリプトを作成させ、人間が電話をかける、またはメールやDMでAIを活用する方が現実的です。
Q4 営業AIを導入する上で、特に重要な組織的な準備は何ですか?
AIの効果を最大限に引き出すためには、データ品質の確保が非常に重要です。CRMに登録された顧客情報の精度を高めたり、過去の提案書や商談結果を体系的に整理したりするなど、データ基盤を整備することが不可欠です。
Q5 テプコカスタマーサービスの事例から、営業AI導入で学べることは何ですか?
営業AI導入は、提案書作成の自動化から始めるのが現実的です。既存のツール(PowerPointアドインなど)との連携を重視し、AIが下書きを作成し、人間が最終判断を行う仕組みを取り入れることが重要です。また、データ品質の継続的な改善と、小規模な実証実験から始める段階的な拡大が成功の鍵となります。
この記事の著者

池田朋弘(監修)
Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。
株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。